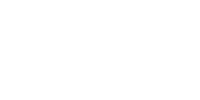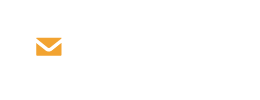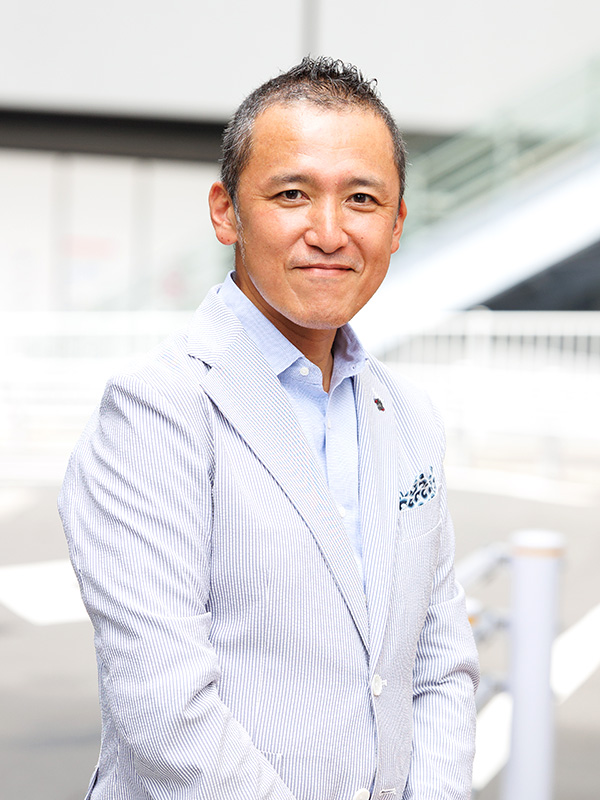そうだ、生活保護を受けよう!
昨今の金融不況の最中、生活自体がたち行かないというご相談をよく受けます。私自身、今年に入ってから生活保護申請事件が非常に増えています。そこで、今回は、生活保護に関する典型的な質問にお答えします。
- 生活保護はどういう場合に利用できますか?
- 憲法25条では生存権が保障され、それを受けた生活保護法1条で、国がすべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うとしています。したがって、この「最低限度の生活」を下回る生活を余儀なくされている人、言い換えれば「最低生活費」を下回る収入しかない人は、原則として皆生活保護を利用できます。
たとえば、東京都の1級地-1の地域(たとえば世田谷区や目黒区)の場合、単身者の最低生活費は、住宅扶助費は上限5万3700円の実額、生活扶助費は約8万円ですから、概ね13万円以下の収入しかない人は差額について生活保護費の支給を受けることができます。
- 借金があると生活保護は受けられないのですか?
- 結論から言うと、借金があるから生活保護を受けられないということはありません。ただし、本来、保護費はあくまで最低生活の維持のために使うものであり、保護費を借金の返済に充てることはできません。ですから、借金がある場合は、弁護士に依頼して自己破産等の手続で借金を整理することを検討すべきです。逆に言えば、「弁護士に依頼して借金を法的に整理する予定である」ということを説明できれば、福祉事務所側も安心して保護を開始することができます。
- 持ち家に住みながら生活保護を受けることは可能ですか?
- 自己所有の土地・家屋に居住していることを理由に生活保護を断られることはあってはなりません。むしろ、厚労省の通知によれば、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合」を除き、原則として世帯の用に供されている不動産は保有を認めることとされています。ただし、平成19年度より、持ち家に居住している世帯で世帯構成員の中に満65歳以上の方がおられる場合(当該世帯構成員の配偶者が満65歳未満である場合を除く)には、生活保護を利用する前にまず各都道府県社会福祉協議会の行う「要保護世帯向け長期生活支援資金」の貸付けを受けることが条件となりました。
この制度は、一定の貸付限度額に至るまで毎月決まった額の融資を受け、限度額に達した段階で貸付けがストップされるという制度です。債務を担保するために不動産に抵当権が設定され、原則として本人死亡時にまとめて償還がなされます。この制度はリバースモーゲージと呼ばれています。
- 住所がない場合には生活保護は受けられないのですか?
- よくこのように誤解している人がいますが、住所がなければ生活保護が受けられないなどというのは全くのでたらめです。生活保護法は住居を有しない人を保護の対象者として予定しています(法19条2項2号)。住居のない人に対する保護を「現在地保護」と言い、その人が現在いる場所を所管する福祉事務所が管轄の実施機関となります(法19条1項2号)。したがって、いわゆる野宿生活者などが福祉事務所に相談に来た場合には、今現在福祉事務所にいることから、福祉事務所の所在地を「現在地」として保護を開始しなければなりません。さらに、厚労省の実施要領によると、「保護開始時において、安定した住居のない要保護者(保護の実施機関において居宅生活ができると認められる者に限る)が住宅の確保に際し、敷金等を必要とする場合」には敷金等の支給を認めても差し支えないとされています(局長通知第7の4(1)キ)。したがって、敷金等のアパートへの転居費用も生活保護費から支給されることになります。
- 生活保護の申請を弁護士に頼むことはできますか? また、弁護士に頼んだ場合、費用はどうなりますか?
- 単独で福祉事務所に生活保護の申請に行っても、いわゆる「水際作戦」と言って、保護受給率を下げるために窓口で相談者を追い返すという違法な対応をする職員もいます。ですから、生活保護の申請も弁護士に依頼する方が確実です。また、弁護士費用の点ですが、現在は、日本弁護士連合会が日本司法支援センター(法テラス)に委託して実施する「自主事業」の一つとして、生活保護申請に関する援助事業が行われています。したがって、生活保護に関しては、法律相談及び生活保護申請について、一定の要件を満たせば弁護士費用は法テラスから支給され、ご本人が弁護士費用を負担することはありません。当事務所にもお気軽にご相談下さい。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。