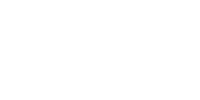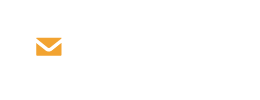成年後見制度
- テレビや新聞で認知症などで判断能力が低下した高齢者が悪徳商法などの被害にあっていることを見聞きしますが、このような被害を防ぐための制度はないのでしょうか?
- 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、契約などの法律行為を適切に行うための判断能力が失われている、もしくは不十分な状況にある場合、本人だけで契約などを行うと、ご質問のように本人に不利な結果をもたらすことがあります。そこで、そのような人を保護・支援するために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動する「成年後見制度」という制度があります。
具体的には、この援助者が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自ら法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援します。
- 成年後見制度にはどのようなものがあるのでしょうか?
- 成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度があります。
まず、「法定後見制度」とは、家庭裁判所が本人の判断能力の低下の程度に応じて後見人、保佐人、補助人と呼ばれる援助者をつける制度です。「後見」というのは本人の判断能力が全くない状態のことで、「保佐」というのは本人の判断能力が失われていないものの、著しく不十分な状態であり、自己の財産を管理・処分するにあたって、常に援助が必要な状態のことで、「補助」は、本人の判断能力が不十分な状態で、自己の財産管理・処分に援助が必要な場合のことです。本人の判断能力が低下した時に、本人ないし近親者等の一定の申立権者が、家庭裁判所に後見・保佐・補助開始の審判を申し立て、家庭裁判所が後見・保佐・補助開始の審判をすると、後見人・保佐人・補助人が選任され、本人のために財産管理などの援助をします。
次に、「任意後見制度」とは、本人の判断能力が十分あるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人と呼ばれます。)に財産管理などに関する事務についての代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した段階で任意後見人が上記契約で決めた事項について本人の援助を開始することになります。また、任意後見開始の段階で、家庭裁判所が任意後見監督人と呼ばれる監督者を選任し、事務処理の適正さが担保されるようになっています。前述の法定後見制度と比較すると、本人が任意後見人を自ら選ぶことができ、さらに援助の内容も自ら決めることができるという点に特徴があります。
以上のとおり、現在、本人の意思や判断能力の程度に応じて多様な制度が整備されていますので、制度の活用にご関心がある方はぜひご相談下さい。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。