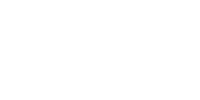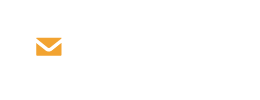遺留分
- 私の家族は、父、母、兄(長男)、私(長女)の4人ですが、先月、父が亡くなりました。父は、生前、父の全財産を兄に相続させる旨の遺言を残していたのですが、この遺言が有効だとすると、私には父の財産を相続する権利が全く無いのでしょうか。
- 死後の財産処分は遺言によって自由に決めることができますが、一定の法定相続人(遺留分権利者)の生活の安定を図る必要などがあることから、遺言の内容にかかわらず、こうした方々に一定割合の相続財産(遺産)の承継を保証する「遺留分制度」(民法1028条以下)という制度があります。
この遺留分権利者というのは、兄弟姉妹以外の法定相続人となります。遺産に占める遺留分全体の割合(総体的遺留分)は、①直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人である場合は遺産の1/3、②それ以外の場合は遺産の1/2、とされており、この総体的遺留分を法定相続分に従って配分したものが各遺留分権利者が有する遺留分(個別的遺留分)となります。
ご相談のケースでは、法定相続人が母と子2人なので上記②にあたり、お父さんの遺産の1/2が総体的遺留分となります。そして、あなたの法定相続分は1/4なので、総体的遺留分の1/4、つまり、お父さんの遺産の1/8(1/2×1/4)があなた固有の遺留分となります(なお、お母さんの遺留分は1/4〔1/2×1/2〕となります)。
したがって、あなたにはお父さんの遺産の1/8を承継する権利(遺留分)があります。全財産をお兄さんに相続させる旨のお父さんの遺言は、あなたの遺留分を侵害していることになります。
もっとも、遺留分を侵害する財産処分が当然に無効となるわけではなく、相続の開始後一定期間内に、遺留分権利者が権利行使(遺留分減殺請求)をすることが必要となります。期間内にあなたがお兄さんに対して遺留分減殺請求をして、はじめてあなたの遺留分(1/8)が保証されることとなるのです。
この期間は「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」(もしくは「相続開始の時から10年」)と非常に限られているので注意が必要です。また、遺留分の割合や金額を算出することが困難なケースや、遺留分減殺請求をしたものの、任意の返還には応じてもらえず、調停や訴訟を提起せざるをえないケースも多々ありますので、「もしかしたら私には遺留分があるのでは」と疑問に思った段階で、なるべく速やかに弁護士にご相談されることをおすすめします。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。