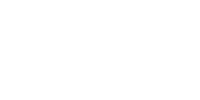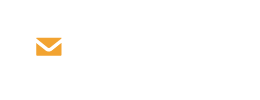遺言書についての法律改正
- 自分が死んだ後、子どもたちが相続でもめないように、遺言を作ることを考えていますが、どのようにして遺言を書いたらよいのでしょうか。公正証書を作らず、自分で書くこともできると聞いたことがあるのですが。
- ご自分に万が一のことがあった場合に備え、遺言書の作成をお考えの方もいらっしゃると思います。遺言が法的に有効と認められれば、残された相続人全員による遺産分割協議を経ることなく、遺言書どおりに遺産が分配されることになりますが、この効果が認められるためには、厳格な要件を満たすことが必要です。遺言者が自分で手書きで遺言を作成することもできますが(「自筆証書遺言」といいます。)、例えば日付を書き忘れたら、それだけで無効です。
しかし、より遺言書を利用しやすいものとするため、2018年7月の民法相続編の改正により、遺言書の方式について、少し要件が緩和されました。たとえば、自筆証書遺言に「遺産目録」(遺産の一覧表)を添付する場合、これまではそれもすべて遺言者が手書きで書かなければならなかったのですが、この度の改正で、預金通帳の写しの添付も認められるようになります(ただし、全ページに署名・押印することが必要です。)。
また、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度も新設されました。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や変造などを防止することもできます。
ただ、要件が緩和されたとはいえ、その要件をきっちり守らないと、せっかく書いた遺言が法的に無効になってしまうことに変わりはありません。
間違ってもそんなことにならないよう、遺言書の作成をお考えの方は、どのような方式、形式で遺言を作成すべきか、必ず一度は、弁護士に相談するようにしましょう。
このQ&Aは、過去の相談をもとに掲載しています。題名横の日付の時点での回答ですので、その後の法改正などにより、現在は内容が変わっている場合もありますので、ご了承下さい。